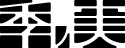気づいたら縁が欠けていたお茶碗。
熱しすぎたお湯を注いで、ヒビが入った湯呑み。
引っ越しの最中、段ボールの中で割れてしまったお皿。
「金継ぎ」と呼ばれる
漆を使ってうつわを繕う方法は
耳にしたことがあったものの
なんとなくハードルが高く、
愛着があるから捨ててしまうのは躊躇うけど、
かと言って使い続けるのも・・・といううつわが
食器棚の奥に徐々にたまっていたとき。
漆芸家・田中早苗さんが
金継ぎ教室を主宰されていると耳にし、
昨年夏ごろから通っています。
ひと月に1回のペースで通い、
うつわのお直しが完了するまでに
かかった期間は、大体1年弱。
塗る、乾かす、固める、研ぐ、
また塗る、乾かす、固める。
1回につきひとつの工程しか進めません。

「欠け」「ヒビ」「割れ」と
そのうつわの状態によって
直す作業工程に多少の違いはありますが
ひとつひとつの作業を積み重ねて、
時間をかけて完成したときには
なんとも言えない嬉しさが
じんわりと込み上げてきました。
元々、金継ぎはお仕事としてやっていらした早苗さん。
「教えてほしい」という要望もあり
4年ほど前から金継ぎ教室を開いています。

今回は早苗さんと、金継ぎ教室に通う
4人の方たちにもお話を伺いました。
お仕事で漆のものを扱っている方、
早苗さんと出会い、漆のものを使うことで
自分も漆に触れてみたいと思うようになった方、
ご家族が骨董品屋を営んでおり、
そこで金継ぎされたうつわの魅力を感じて
自分でも直せるようにと通っている方など。
通い始めるきっかけはそれぞれ違えど、
皆さんに、金継ぎの良さとはなにか尋ねてみました。
「同じ種類のうつわを何枚も揃えていて、
割れていないものもあるのに
金継ぎしたものばかりを思わず使ってしまう」
「壊れてしまったことはショックだけど、
直った途端に愛情がわいて、割れていないものより
金継ぎしたもののほうがよく感じる」
「欠けてしまったたわびしさが、生き返った嬉しさに
変化して、以前よりずっと愛着をもって使うようになった」
「ほかの人がつくったうつわだけど、
自分の手が入った感じが嬉しい」
時間と愛情をかけて金継ぎすることで、
元々大切にしていたうつわの存在が
より愛しいものへと変化している様子。
金継ぎができると思ったら、うつわを割ってしまったときの
罪悪感が少し薄れる、と笑う方も。

また、金継ぎの使う材料はどれも自然のものだったり
台所で使うような、身近で素朴なもの。
そこが好きという声もありました。
漆とはそもそも、「ウルシ」の木の幹から採取される樹液。
うつわの欠けた部分を埋めるのに使う、
刻苧(こくそ)と呼ばれるパテのようなものは
小麦粉に水を加えて練り、さらに漆、木粉、麻綿を混ぜて作ります。
小麦粉を使うと知ったときは少し驚きましたが、
食べものを乗せるうつわを繕うのに
口にして安全なものを使うのは
よく考えたら自然なことなのかも。

早苗さんが以前、修理の依頼を受けたうつわは
接着剤でくっつけられており、はがそうとしたら
化学物質の嫌な匂いがたったことがあるそうで、
食べものを乗せることを想像すると、
やっぱり自然なものを使いたいという気持ちが
自ずとわいてきます。
修理を依頼されたときには、必ず直したい理由を尋ねると
早苗さんは言います。それは、改めて買い直したほうが
安くても、金額より、想いのほうが重要と考えるから。
教室に通う前に早苗さんから聞いた、戦後すぐのころ、
物資が少ない時代に作られた漆の重箱のお話が印象に残っています。
紙などありあわせの材料で量産して
漆も簡単に塗ってあるような仕上がりだったけど、
それでも漆のお重でお正月の気分を高めようとした
当時の時代背景が見えたそうです。
そのものが持つ背景を必ず尋ね、どこまでお直しするか。
漆芸家である早苗さんは、
「漆を知ってほしいというのが根本にあるから、
漆じゃないものを使ってまで直すことに
自分は意味を感じない」と話します。

実際、金継ぎの手法や使う材料には
決まりや正解があるわけではなく、
金継ぎする方々それぞれ異なるそう。
さらに、「金」継ぎと呼ばれるものの
仕上げには必ずしも金を使うわけではなく
銀や錫など他の金属粉や、赤などの色漆で
仕上げることもあります。

その仕上がりも、段差なくなめらかに
なっているほうがいいこともあれば、
漆がはみ出していたり、凹んだ部分が残っていたりと
ちょっと雑とも捉えかねないくらい、
大らかに直してあるほうが似合うものもあったり。
最後に蒔いた金属粉を磨くのも、磨かないままにするのも。
すべてその直す方の感覚や感性に委ねられます。
繕ったその姿には、新品のものとは違う美しさがあります。

古い骨董のうつわだと、修繕された部分に
青海波が描かれていたり、他のうつわの欠片と
コラージュのように合わせたりするものもあるのだとか。
新しいものがすぐに手に入る、今の世の中。
形あるものいつか壊れる、という言葉もありますが
それを繕って、新しい形を創作のように自分の手で
生み出せるのは、金継ぎの魅力のひとつだと感じます。
時間をかけて繕って、生き返らせたうつわと
また、新たな時間を重ねていく。
ものを大切にする気持ちをも、こうして育てていける技術を
身につけられるありがたみを感じながら、
また別のうつわを直しに、教室に通っています。
文:松倉奈弓
写真:大木賢